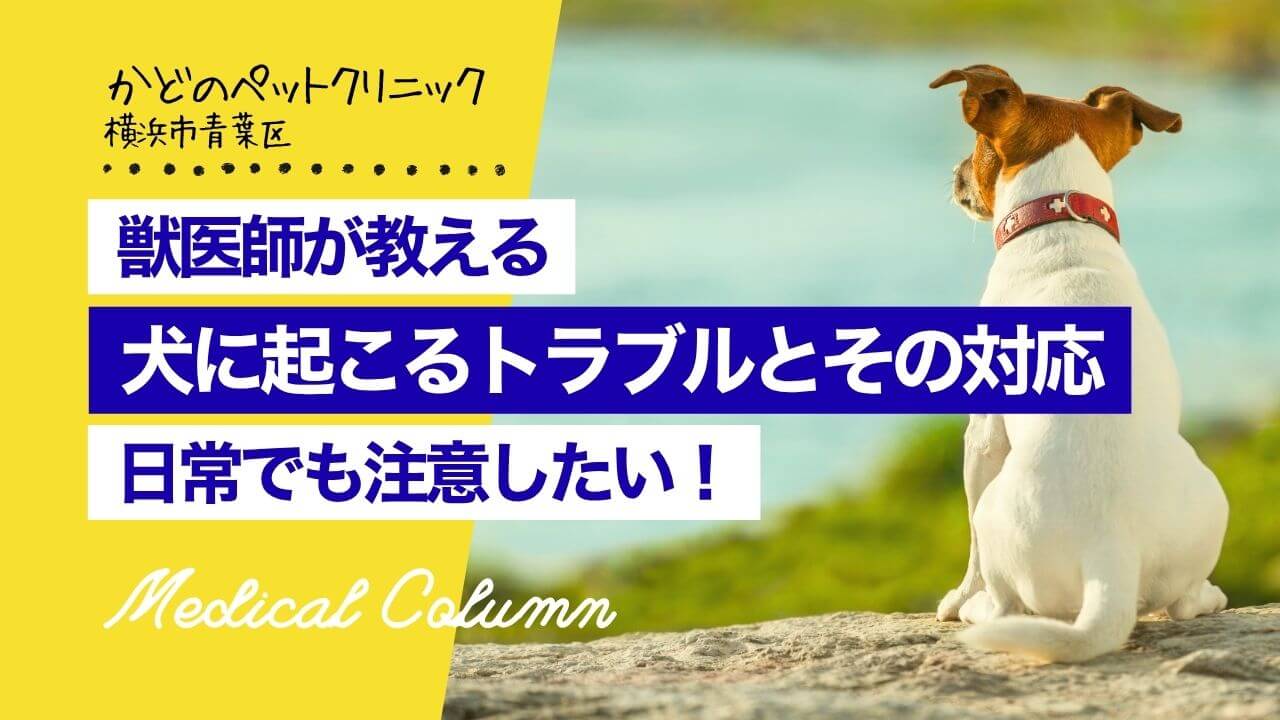こんにちは!
朝晩の風が少し冷たくなり、木々が色づき始めると、いよいよ「食欲の秋」の到来です。
私たち人間にとって秋は、食卓が豊かになる季節。
甘みが増したさつまいもやホクホクのかぼちゃ、みずみずしいりんごなど、
自然の恵みがたくさん収穫される時期でもあります。
そんな季節を、家族の一員であるわんちゃんやねこちゃんとも一緒に楽しみたい、
そう考える飼い主さんは多いのではないでしょうか。
でも、ちょっと待ってください。
人が「おいしい」と感じる食材の中には、犬や猫の体には適さないものもあるのです。
今回は、秋に楽しめる「OKな食べ物」と「NGな食べ物」、
そしてじょうずな与え方について、
オンラインで相談から自宅での往診をかなえる『往診専門 ノートル動物病院』が
獣医師の立場からアドバイスをお届けしてくれます!
オンラインで相談から自宅での往診をかなえる『往診専門 ノートル動物病院』
ノートルは、獣医師と動物看護師がみなさまのご自宅を訪問し、
動物病院に通院することなくペットの健康管理・診療を行うサービスです。
お問い合わせやご予約は公式LINEから行うことができます。
プロフィール紹介|往診専門の動物病院 ノートル 獣医師 小澤 裕里子先生

都内・神奈川の一次診療動物病院勤務を経て、沖縄でTNR活動に特化した保護医療に従事。
その後、グループ動物病院で予防医学に注力し、
現在は往診を通じて自宅での動物ケアをサポートしています。
幅広い現場経験を活かし、飼い主様と動物に寄り添った医療を提供しています。
秋の味覚で「与えてOKな食材」

以下は、加熱する・種や皮を取り除く・味付けしないなどの
注意を守れば、愛犬・愛猫にも楽しんでもらえる食材たちです。
さつまいも
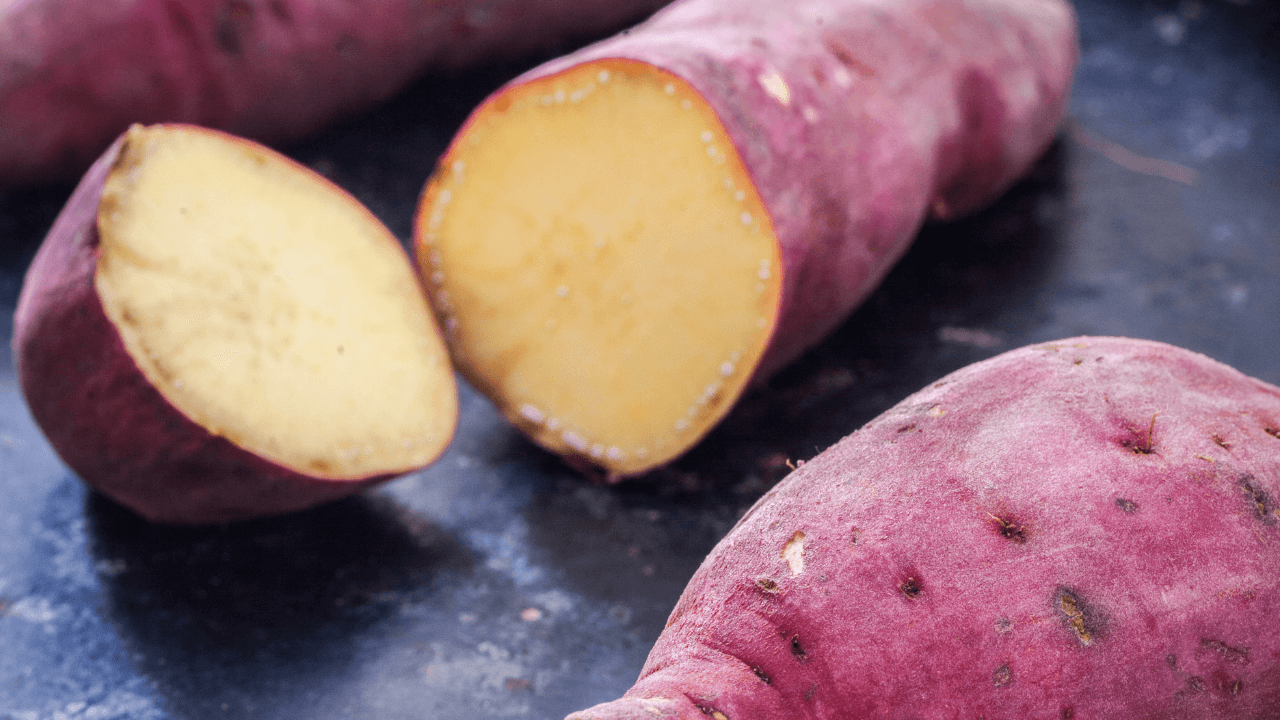
食物繊維やビタミンC、
ビタミンB6、カリウムなどを含む
栄養豊富な野菜です。
適量であれば、
整腸作用や便通の改善にも
一役買ってくれることがあります。
甘みもあって、好きな子も多い食材です。
① 加熱して与えること(生はNG)
生のさつまいもは消化しづらく、下痢や嘔吐の原因になります。
必ず茹でるか蒸すなどして、柔らかくしてから与えてください。
油で揚げた大学芋やスイートポテトは糖分・脂質が多く、犬猫には不向きです。
② 小さくカット or つぶして与える
そのままだと喉に詰まらせてしまうリスクがあります。
とくに小型犬やシニアの子には、つぶしてペースト状にしたほうが安心です。
③ 与えすぎ注意
さつまいもは糖質が高く、与えすぎると肥満の原因になります。
目安としては、体重5kgの犬や猫に対して1日あたり10~15g程度までを目安にしましょう。
④ 持病がある子は獣医さんに確認を
糖尿病や腎臓病などを持つ犬猫には、与えないほうが良いケースもあります。
心配な場合は、かかりつけの獣医師に相談してからにしましょう。
かぼちゃ

ビタミンA(βカロテン)やビタミンE、
食物繊維、カリウムが豊富な野菜。
とくに抗酸化作用のある成分が多く、
免疫力アップや皮膚・粘膜の健康維持に
役立つといわれています。
便秘気味の子には整腸サポートにも
期待できます。
① 必ず加熱して与える(生はNG)
生のかぼちゃはとても固く、消化にも負担がかかります。
蒸す・茹でるなどして柔らかくしてから与えましょう。
電子レンジで加熱するだけでもOKです。
② 種・ワタ・皮は取り除く
種やワタは消化に悪く、喉に詰まらせる危険もあります。
皮もかたいため、中身の黄色い部分のみを与えましょう。
③ 味付けなしで
人用のかぼちゃの煮物やスープは砂糖・塩・出汁などの味付けがされているため、
犬猫にはNG。味付けなしの素煮が基本です。
④ 与えすぎ注意
甘みがあるかぼちゃは、つい多めにあげたくなりますが、
糖質が多いため肥満や血糖値上昇のリスクも。
目安としては体重5kgで1日10~15g程度にとどめておきましょう。
⑤ 持病のある子は獣医師に相談を
特に糖尿病・腎臓病などのある子には注意が必要です。
与える前にかかりつけ医のアドバイスを仰ぎましょう。
りんご
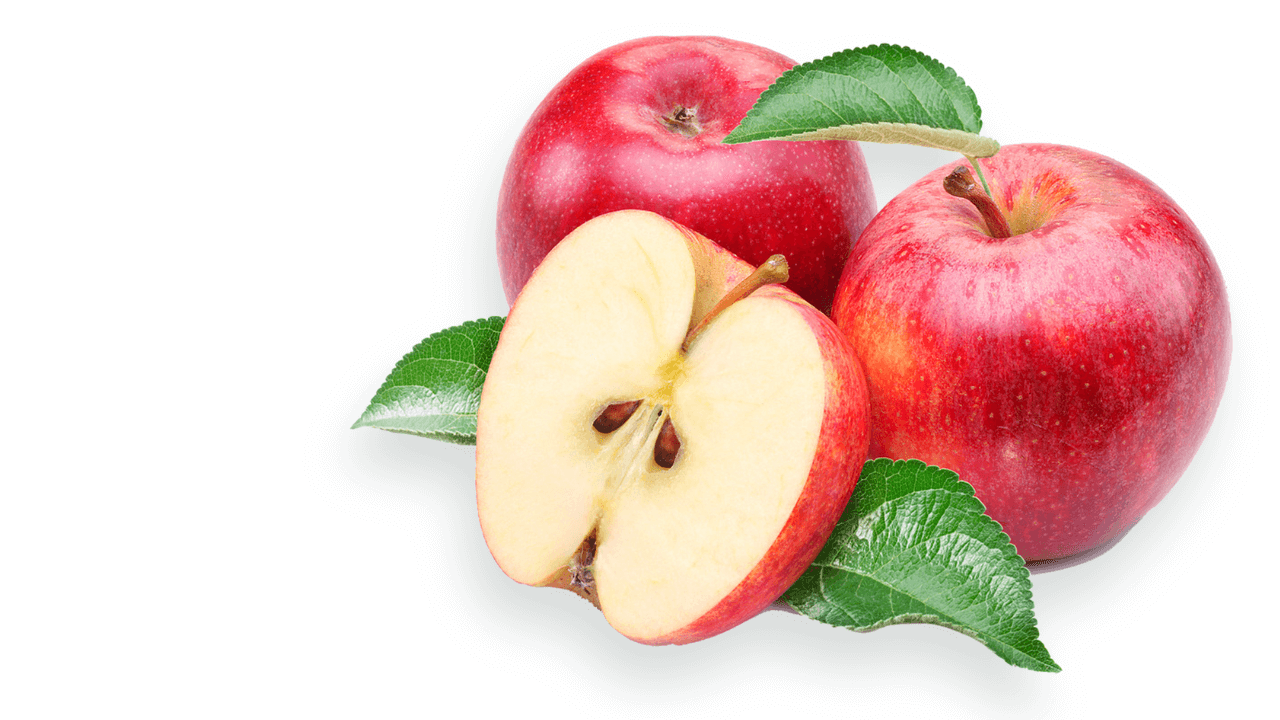
食物繊維(ペクチン)やカリウム、
ビタミンCなどが含まれ、
腸内環境のサポートや軽い利尿作用、
免疫維持に役立つといわれています。
なにより香りが良く、
食欲が落ちた子にも食べやすい
自然なおやつとして人気です。
① 種・芯・ヘタは絶対NG
りんごの種には「アミグダリン」という成分が含まれており、
体内で微量の有害物質(シアン)を発生させることがあります。
芯やヘタも硬く、消化不良や喉詰まりの原因に。
必ず果肉の部分だけを与えましょう。
② 皮はできればむく
皮にはポリフェノールなどの栄養がある反面、
農薬が残っている可能性や、皮の繊維でお腹がゆるくなる子もいます。
できるだけ皮をむいて与えるほうが安心です。
③ 小さくカット or すりおろして与える
そのままだと喉に詰まらせる危険があります。
小さく切るか、すりおろす、細かく刻むなどして与えてください。
消化力の弱い子には、少しレンジで加熱して柔らかくするのもおすすめです。
アップルソースのようにして、普段のごはんに少量添えてもOK。
④ 与えすぎ注意(糖分多め)
果物のなかでも糖分が多いため、肥満や糖尿病のある子には不向きです。
目安
小型犬(2〜5kg)は34g〜67g
中型犬(6〜15g)は77g〜153g
大型犬(20〜50kg)は189g〜376g
あくまでも「おやつ」として楽しむ程度にしましょう。
⑤ 持病のある子は獣医師に相談を
特に糖尿病・腎臓病などのある子には注意が必要です。
与える前にかかりつけ医のアドバイスを仰ぎましょう。
また少量のタンパク質が含まれているため、アレルギーにも注意が必要です。
梨

梨には水分がたっぷり含まれており、
カリウムや少量の食物繊維も含まれます。特に暑さが残る初秋には、水分補給の
サポートとしても期待できます。
ただし、栄養価が高いわけではないので、「健康のため」というよりは季節のおやつとして考えるのがよいでしょう。
① 種・芯・皮はNG
梨の種や芯は硬くて消化が悪く、誤って飲み込むと腸閉塞や窒息の危険も。
皮も消化しにくいため、皮をむいて果肉部分だけを
小さくカットして与えるのが鉄則です。
② 味付け・加工品は避ける
梨ゼリーや缶詰などの加工品には砂糖や添加物が多く含まれ、
犬猫にとっては不適切。生の梨のみ、味付けなしで与えましょう。
③ 与えすぎ注意(果糖が多め)
梨は水分が多くてヘルシーに見えますが、果糖(フルクトース)が多いため、
与えすぎは肥満や血糖値上昇の原因になります。
体重5kgあたり5〜10g(薄切り1〜2枚程度)を上限にしましょう。
④ お腹がゆるくなる子も
水分が多いぶん、お腹が弱い子にとっては下痢の原因になることもあります。
初めて与えるときはごく少量から試し、体調に変化がないか様子を見ましょう。
さんま(秋刀魚)

さんまは良質なたんぱく質に加え、
DHA・EPA(オメガ3脂肪酸)、
ビタミンB群、カルシウム、鉄分などを
含んだ栄養豊富な青魚です。
これらは被毛や皮膚の健康、
脳や心臓のサポートにもつながるとされ、犬猫にとってもうれしい成分が
詰まっています。
① 生のサンマはNG(必ず加熱)
生魚には寄生虫(アニサキスなど)や細菌のリスクがあります。
必ず火を通してから与えましょう。
焼く・蒸す・茹でるなどがおすすめですが、塩焼きはNGです。
② 味付けは一切なしで
人用の塩焼き、醤油煮、みりん干しなどは塩分や糖分が多く、
犬猫の体には負担となります。味つけなしで調理することが絶対条件です。
③ 骨は取り除く(とくに小骨)
サンマは骨が細かく、喉や食道、胃腸を傷つける恐れがあります。
必ず丁寧に骨を取り除き、ほぐして与えるようにしましょう。
小型犬や猫は特に要注意です。
④ 与える量は少量を目安に
脂が多い魚なので、与えすぎると下痢や膵炎のリスクも。
体重5kg程度の犬猫なら、ごく少量(10~15g)程度が目安。
あくまで「トッピング」や「おやつ」として与えましょう。
⑤ 内臓・頭・皮は与えない
サンマの内臓には苦味成分や不飽和脂肪酸が多く含まれ、消化に悪い場合もあります。
頭や皮も硬く、トラブルの原因になりやすいため、身の部分だけを使用するのが安全です。
秋だけど「絶対にNGな食材」

見た目や香りはおいしそうでも、犬や猫にとっては危険な食べ物もあります。
ぶどう・レーズン
ごく少量でも急性腎不全を引き起こす可能性あります。
体質により反応に差があるため、絶対に与えないようにしましょう。
ぶどうを乾燥させたレーズンやドライフルーツも同様に危険です。
むしろ小粒なぶん、少量でも中毒量に達しやすいため、
パンやお菓子に入っているものにも注意が必要です。
ぶどうやレーズンを食べてから数時間~1日以内に、以下のような症状が現れることがあります
嘔吐・下痢
食欲不振
元気消失
腹痛や震え
尿が出ない、または極端に少ない
けいれんや昏睡(重度の場合)
腎不全が進行すると、命にかかわることもあるため、
誤食が疑われたらすぐに動物病院へ連絡、受診してください。
銀杏(ぎんなん)
銀杏には「メチルピリドキシン(MPN)」という、
ビタミンB6の働きを阻害する成分が含まれています。
これが神経系に作用し、けいれんや昏睡などの中毒症状を引き起こす原因になります。
中毒量には個体差がありますが、
犬:数粒程度でも危険
猫:犬より少量でも発症の可能性あり
体格が小さいほどリスクは高く、子犬・子猫にはとくに注意が必要です。
また、調理された銀杏だけでなく、落ちている未熟な実や果肉部分も危険です。
散歩中の拾い食いで誤食するケースが後を絶ちません。
銀杏が落ちている季節は特に拾い食いに注意しましょう。
銀杏中毒の症状は、食後数時間〜半日以内に出ることが多く、
以下のような兆候が見られます
嘔吐・下痢
ふらつき
筋肉のけいれん
過度な興奮・鳴き続ける
意識混濁・けいれん発作
呼吸困難、昏睡(重篤例)
これらの症状が見られたら、すぐに動物病院へ!
治療が遅れると、命に関わる可能性があります。
イチジク
イチジクの果肉や葉、茎には「フィシン(Ficin)」や「ソラレン(Psoralen)」といった
有害物質が含まれています。
これらの成分は、人間にとっては無害な場合が多いですが、
犬や猫の体には強い刺激や毒性となる可能性があります。
とくに、未熟なイチジクや葉・茎をかじった場合のほうが、
症状が強く出やすいとされています。
生の果実だけでなく、イチジクを使ったジャム・焼き菓子・ドライフルーツなどの
加工品も与えてはいけません。
糖分や添加物が多く含まれ、イチジク由来の成分が残っている可能性もあります。
誤ってイチジクを口にした場合、以下のような症状が現れることがあります
嘔吐・下痢・食欲不振
よだれが増える
口内炎・口の中の腫れや痛み
皮膚に触れると赤みやかゆみ(接触性皮膚炎)
重症例では呼吸困難や脱水症状も自然の中には、
蚊やダニなど、ペットにとって厄介な虫がたくさんいます。
蚊によるフィラリア症や、ダニが媒介する病気のリスクも考慮する必要があります。
キャンプに出かける前には、ペット用の予防薬を使用するのが最も効果的。
また、虫除けスプレーや虫除け服を使うことで、さらにリスクを減らせます。
季節の恵みを、愛をもってシェアする

人も動物も、秋はなんとなく気持ちがほっと緩む季節です。
そんなとき、愛犬・愛猫と一緒に「おいしいね」と顔を見合わせる時間が生まれたら、
それはきっと何よりの幸せではないでしょうか。
「これは与えて大丈夫かな?」と迷ったときは、遠慮せず獣医師に相談を。
命を預かる飼い主さんにとって、一番大切なのは“安全”と“健康”を守ることです。
この秋、愛するパートナーと「実りある思い出」がたくさん作れますように。
次回予告:冬のはじまりに備える~愛犬の体調管理~
次回のテーマは、「冬のはじまりに備える~愛犬の体調管理~」
・冷えからくる愛犬の不調の対策
・食欲の秋から一転「冬の体重増加」に注意
・乾燥による皮膚トラブルの兆候
11月になると、暦の上では「立冬」を迎え、
朝晩はぐっと冷え込み、空気も乾燥してきます。
人間と同じように愛犬たちにとっても、体調を崩しやすい季節の変わり目!
ここでしっかり備えておくことが、冬を元気に乗り越えるポイントです
そんな重要なポイントを詳しく解説します!
ぜひ、お楽しみに〜!
株式会社ノートル
ノートルは、獣医師と動物看護師がみなさまのご自宅を訪問し、
動物病院に通院することなくペットの健康管理・診療を行うサービスです。
お問い合わせやご予約は公式LINEから行うことができます。
対応エリア
東京都内
埼玉県・神奈川県の方もご相談ください
※対応エリア順次拡大予定
- 診療時間:10:00 – 18:00
- 休診日:年中無休
- 公式サイト:https://notre-pethealthcare.com